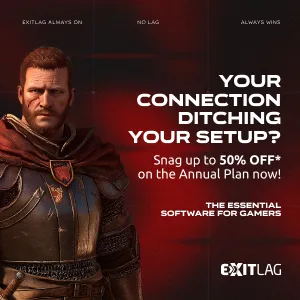| ID: 731680 | |
| キルヒネの記録 | |
|
NPC
レベル: 1 HP: 63 攻撃半径: 0m | |
|
ダイアログ: - 目次 - 魔族の若きディーヴァへ 第1章:最初の世界 第2章:龍族の覚醒 第3章:千年戦争 第4章:和平提案 5章:大崩壊 第6章:混乱とパンデモニウム建設 第7章:アビスの発見 第8章:アビスでの戦争 魔族の若きディーヴァへ はるか昔アトレイアはひとつだった。アイオンもひとつだった。魔族と天族の区別も無く、人間だけが存在していた。すべての人間が永遠の塔であるアイオンを守り、それに従い龍族と戦っていた。 しかし、すべての人間が同じ姿、同じ目標を持っていた時代も今は昔。もはや、そのような時代を迎えることは二度とない。 我々が住まうこの大地は、本来あるべき世界の一部でしかない。大崩壊の後、我々はこの暗く不毛な大地に取り残された。我々に残された道は、この寒くて暗い不毛の大地に適応するしかなかった。自らの姿さえ変わり果て、やっとのことで生き残れた我々を待ち受けていたのは、更なる試練と危機であった。 包容や許容では、平和をもたらすことなどできない。その昔、我々が包容の道を選ばず、徹底抗戦をしていたならば、アトレイアが二分される事もなかっただろう。我々は二度と同じ過ちを犯してはならない。たとえこの地が二分された仮の故郷であっても最後の1人まで戦うべきである。 わがの名はキルヒネ。大崩壊の前から戦ってきたディーヴァである。 龍族との戦いを、大崩壊を、天族との戦争の始まりをこの目で見てきた私は、魔族が成すべきことは何か、向かうべき道が何なのか知っている。 大崩壊の災いを招いた天族を許してはならない。魔界と天界が共存することなどできないと知った以上、彼らに自らの行いを償わせるべきだ。 今日のディーヴァたちは過去の悲劇を知らない。オードが枯渇し、崩壊を迎えるという警告にも他人事のようにしか認識できていない。 魔族がいかに大きな危機に立ち向かっているのか、過去の事件から学ぶべきだ。そして真の魔族のディーヴァとしていきることが、どういうことか学んでほしい。 第1章:最初の世界 太古のアトレイアは楽園であった。世界中がアイオンの光に満ちあふれ、今のような闇も寒さも無かった。 大地には畑と牧場が広がっていて、何もかも満たされていた。その時の自然は人間にとって祝福であって、決して命を脅かすような存在ではなかった。 しかし、人間を脅かすものが無かったわけではない。現在でも我々を脅かす龍族が人間を支配していた。知性は対等であっても、はるかに劣る肉体を持つ人間は、龍族の支配から逃れられなかった。 だが、龍族に君臨されてもなお、人間は独自の文化を発展させ、共同体を築き上げた。アイオンに対する信仰が、すべての生活と文化の基本となった。アイオンへささげる賛美の言葉が詩となり、歌となり、アイオンのために建てた神殿が、他の建築物にも影響を与えた。 このような平和は永遠に続くかと思ったが、それは龍族の黒い野心が表面化するまでのことだった。 第2章:龍族の覚醒 太古のアトレイアに生息した龍族はドラカンだった。彼らが他の種族を支配できたのは、極めて優れた肉体を持っていたからだ。 凶暴なライカンとクラルでも龍族にはかなわなかった。人間も龍族の目を避け、出来るだけ龍族に見つからない場所に住もうと必死だった。 ドラカンは権力と富を求め続けた。より広大な領地を望み、より多くの人間と亜人種の支配を望んだ。そしてなによりも強大な力を望んだ。より強力な肉体と卓越した魔力を手に入れようと、絶え間ない努力を繰り返した。 その努力の結果、覚醒の時を迎えたドラカンが現れた。彼らは以前より優れた知性を備えただけではなく、新しい肉体も手に入れた。 より巨大な体に、翼が生えた姿に生まれ変わったのだ。 覚醒したドラカンは、自らをドラゴンと名乗った。そして彼らの中でも特に優れたドラゴンが現れ、徐々に龍族の支配者となった。 龍族の支配者になった5人のドラゴンは自らを「龍帝」と称した。 龍帝の力は、以前とは比べ物にならないものであった。彼らの支配のもと、龍族はより強大になり、人間と亜人種は、彼らの暴政に虐げられるようになった。 しかし、アトレイアのすべてを手に入れても、なお富と権力に対する龍帝の渇望は衰えることはなかった。 そしてとうとう彼らは、自分達が強力な富と権力を求める原因に気づいてしまった。それはアイオンが彼らの上にいたからであった。 愚かにも、龍帝たちは自らがアイオンを超えられると信じていた。そして、アトレイアからアイオンを追放し、自らが神になろうとしたのだ。 第3章:千年戦争 龍帝が現れた時、ライカンやクラルなどの亜人種は、すでに龍族に屈服していた状態だった。むしろ彼らは龍帝がアイオンに反旗を翻したときに、なんら抵抗もなく龍族の命令に従ったのだ。 人間だけがアイオンに反旗を翻した龍族に抵抗した。 アイオンは自らに従う人間を守り、龍帝を裁くために十二柱神を人間に遣わした。 そして自らを守るために結界を作った。結界は純粋なオードの力で作られているので、オードに反する龍族は結界の中に入ることが出来ない。 そして、十二柱神は多くの人間を結界の中に避難させ、龍族に対抗できるよう、人間達を組織的に訓練し始めた。 十二柱神の訓練を受けると、人間も龍族のように覚醒し始めた。背中に翼が生え、オードの力を扱えるようになったのだ。また、当時は知られなかったが、老いることのない永遠の生命も与えられた。 覚醒した人間はディーヴァと呼ばれた。ディーヴァに覚醒することが十二柱神の祝福だと思った。多くの人間達がディーヴァに覚醒し、私もまたその中のひとりであった。 ディーヴァの登場により戦況は大きく変わった。ドラカンとディーヴァが対等に戦えるようになったのだ。 私もまた、ルミエル神から授かったスペルブックを持ち、オードの力を使ってアイス チェーンで縛りながらドラカンと戦った。 ディーヴァとドラカンの力に差はなかった。十二柱神と五龍帝の力も拮抗しているため、人間と龍族は一進一退の攻防を繰り広げた。 私の息子と孫、ひ孫のみならず、多くの子孫たちが生まれては散った長い歳月のあいだ、私はディーヴァとして気の遠くなるような戦いを続けた。 アイオンを破壊しようとする龍族と、アイオンを守ろうとする人間の長い戦争は、千年ものあいだ、続いた。 第4章:和平提案 戦争を終結させる動きは、思いがけないところから始まった。龍帝を最も憎しみ、敵対的だったイズラフェル神が、龍帝との和平を提案したのである。 イズラフェルは戦争を始めた理由が何であったのか、つまり、龍族を滅亡させることではなく、アイオンを守ることが目的であったということを思い出せと言った。 イズラフェル神の主張は、他の神たちに大きな物議をかもしだした。ディーヴァと人間たちは神々の意見の衝突に混乱しながらも、彼らも賛成派と反対派に分かれて激論を繰り広げたが、その決着はつかなかった。 私は、龍族との和平は絶対にありえないと考えていた。アイオンを破壊しようとした種族と、どうして平和を論じられようか。 どんなことがあっても和平の提案は防ぐべきだと思ったが、何をどうすれば良いかもわからない私は、熱心に教えを受けたルミエル神を訪ねた。 神の居場所に入る前に、老いた声が聞こえてきた。アスフェル神の声であった。 「いったいイズラフェルは何を考えているのか?いくら戦争が長引いたといえども龍族と和平をしようとするとは!アイオンの神聖さを否定する異端の群れと協定を結んだら、去る千年に渡る人間とディーヴァの犠牲者はいったい何だったというのだ!」 アスフェル神の声を聞いて、愚かにも私は安心した。神々があのように反対する和平が成立するはずはないと思ったのだ。 だが、イズラフェル神は他の神の意見を全く聞くこともなく、シエル神を説得することだけに、全力を注いだ。 結局、アイオンを守る本来の目的を考えろという言葉にシエル神は説得された。塔の守護者である二柱神が和平に賛成してしまえば、他の神たちはそれに従うしかなかったのである。 私だけでなくレギオンの仲間たちも、どうしても龍族との和平を受け入れられなかった。我がレギオンはアイオン塔へ急いで向かい、翼を広げてシエル神とイズラフェル神に嘆願した。 しかし、すでに下された決定を覆すことはできなかった。 5章:大崩壊 来てはならない和平の日が訪れた。 シエル神とイズラフェル神は、事前に五龍帝と合意したとおり、アイオンの周囲の結界を解除した。五龍帝はすべての武器を外して来た。 約束の場所に入る五龍帝を見た瞬間、私は必死に涙をこらえた。これは和平でなく屈辱だ。震える仲間の肩が目に入る。我がレギオンの兵士たちは、怒りを堪えながら、そこに立ちつくしていた。 十二柱神と五龍帝が向かい合っていた。事前協議に沿った形式的な話が交わされ、和平の儀式が進められていた。 その時だった。突然、龍帝の一人が倒れるや否や、混乱が始まった。 怒号と悲鳴が飛び交う中、第一龍帝フレギオンが空に飛び上がったのを見た。次の瞬間、目が見えなくなるほどの強烈な光が放たれた。 その後は、轟音と混乱、悲鳴の渦であった。地面が割れるような激震が走り、塔の周囲にあったもの全てがどこかに吹き飛ばされていった。 その中でアイオン塔が真っ二つになるのが見えた。私は目の前の光景がとても信じられなかった。崩れ去るアイオンのかけらを見て呆然と立ち尽くしていると、荒々しいオードの気流に巻き込まれた。 だんだん気を失っていく私の目に最後に映ったのは、大きな翼を広げたシエル神とイズラフェル神が再び結界を張る姿だった。 第6章:混乱とパンデモニウム建設 気がつくと、私と仲間たちは、のちにアルトガルドと呼ばれる場所にいた。ショックと混乱が落ち着くと、私たちは状況を把握しようとした。しかし、私たちに突きつけられた事実は、到底信じられない、信じたくないものであった。 結界がまた張られたため、龍帝たちはオードに耐えきれず結界の外に逃げた。だが、アイオンと共にアトレイアが破壊された。 そして、大崩壊の場にいた数多くのディーヴァたちと、シエル神、イズラフェル神が消滅した。 アビスを発見した後でわかったことだが、シエルとイズラフェルは半分に分かれたアトレイアが破壊されないように最後の力を振り絞った。そして、その場にいたディーヴァと他の神をアトレイアの北と南に移動させ、力尽きたのだ。 私が着いた場所は北側であり、アイオンの光は絶え、破壊された隙間からかすかに入ってくる星の光しかない、闇の世界に変わっていた。 寒さと闇は人間とディーヴァをひどく苦しめ、豊かだった土地は不毛なものに変わった。何より、アトレイアに満ちあふれていたオードが著しく減少していた。 多くの人間とディーヴァたちが絶望したが、幸いにもアスフェル神をはじめとした五柱神が私たちと一緒だった。 前とは違う、あまりにも不毛な環境に適応するために、私たちの姿は少しずつ変化していった。 はじめは、皮膚が徐々に青白く変わった。更に歳月が経つと、手や足の爪が、かぎ爪のように鋭くなった。これ以上変わらないと思ったが、ついには背中にたてがみが生え始めた。 変わり果てて、自分が別人になってしまったということに、心の奥底でひそかに苦痛を感じた。 しかし、そういった逆境を耐え忍び、我々はアトレイアを復旧していった。再建と繁栄の象徴として新しい首都のパンデモニウムを建設した時は、感激の涙を流さずにはいれなかった。 第7章:アビスの発見 大崩壊から長い歳月が流れた。 アトレイアは平和で、龍族との戦争や大崩壊は人々の記憶から徐々に忘れ去られていった。たまに問題を起こすライカンを除けば、魔族を脅かすものは何もなかった。 そんなある日、奇妙なことが起こった。 地面に埋まっていたはずのアイオン塔のかけらが光を放ち、空に浮かび上がり始めた。そして、それに近付いた人々が次々と消えていったのだ。 パンデモニウムでは塔のかけらに接近することを厳格に禁じ、アルコンたちを派遣して調査を始めた。 調査して明らかになったことは、アトレイアとは完全に違った新しい空間に行けるということだった。 新しく発見された異空間を探査するために多くのディーヴァたちが出向いた。各地にある浮遊島を一つずつ探険し、アビスと呼ばれる異空間について徐々に明らかにしていった。 だが、アビスはとても危険なところだった。すべての破片が同じ場所につながっているわけではなく、入った入口が突然閉じ、永遠に帰れなくなったディーヴァたちも現れ始めた。 だが、アビスの本当に驚くべき点はそれではなかった。沈黙の審判官としてアルコンたちの相次ぐ失踪を調査するためにモルヘイムに行った私は、はっきりとこの目で彼らを見た。 大崩壊以前の私たちと同じ姿をした、アトレイアの南側から来た者たちを。 彼らはアビスを介して私たちの世界へ来た者たちだった。 私が発見した時、彼らはジケル神と話し合っていた。 デルトラスという彼らのリーダーは、もうこれ以上の衝突は望まないので、自分たちの世界へ静かに帰ると話していた。ジケル神も彼らに危害を加えるつもりはないように見えた。 だが、ジケル神の傲慢な性格が問題であった。 彼らが崇めるネザカン神を呪うなら帰してやると、冷やかすような言葉を口にした途端、デルトラスは頭を上げてジケル神に呪いをかけた。 その後、すさまじい戦闘が起こった。そして、その戦闘がまさに天魔戦争の始まりだった。 第8章:アビスでの戦争 デルトラスがモルヘイムで死を迎えた後、天族との戦争が始まった。 はじめは単純な復讐と報復の繰り返しだったため、私はこの戦争が長くなるとは少しも思っていなかった。 離れたまま長い歳月を過ごしたが、魔族と天族は本来一つではないか。 だが、状況は全く予想しない方向に流れた。アビスが存在する限り、アトレイアの存続が脅かされるということがわかったのだ。 唯一の解決方法は、天界に残ったアイオン塔を破壊することだけだった。 龍族との千年戦争に匹敵するほどの、新たな戦争が始まったのだ。 そして、天魔戦争に呼応するかのごとく、龍族が現れた。以前の敵だったドラカンだけでなくナーガとドラコニュートまで。相変らず彼らの目標はアトレイアとアイオンだった。 二千年を越える長い歳月を振り返ると、最初の千年は龍族を相手に戦場で過ごした。 その後の歳月は、崩壊したアトレイアを復興してパンデモニウムを繁栄させることに、この身を捧げた。それらはすべてディーヴァとして人間を守るためであった。 これほど長い歳月を奉仕したが、私の任務はまだ終わらないようだ。私は神の祝福に報いるため、ペンを置いて、再度スペルブックを手に取るべき時が来たからだ。 アトレイアの北と南は、もはや相手を倒さねば自分の身が危ない状況に置かれた。 その昔、十二柱神が龍族に対抗するためにディーヴァを教育したように、天族と魔族はお互いを倒すためにテンペルでディーヴァを育成している。 天族と魔族は大崩壊の原因をお互いのせいにし、自分たちこそがアトレイアの真の主だと主張している。 しかし、天族と魔族、龍族が入り乱れる三つ巴の戦場で、どの陣営も勝機を見出せない拮抗した状態が続いている。 生存への欲望と怨恨にあふれた戦場で、果たして君はどちらの側に立つのだろうか。 | |
このページのデータを編集するにはログインしてください。
BBCode
HTML
コメントを投稿するにはログイン